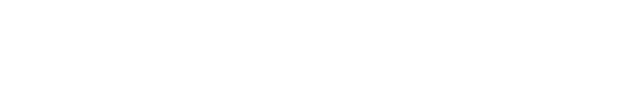心臓病を持つ人に適切な運動療法のすすめ
こんにちは。院長の大口志央です。暑すぎた夏も終わり、だんだんと冷涼な日が多くなってきましたね。でもすぐに冬になってしまうんでしょうか。
さて今回は心疾患を持つ人の運動の意義について取り上げてみたいと思います。
「心臓に負担をかけないように動かない方がいい」
かつては心疾患に罹患した方々はこのように考えられていました。心臓が悪いと少し動くだけで息切れがしたり呼吸が乱れたりします。心臓病が原因で循環のバランスが崩れた状態を心不全といいますが、心臓の余力を超えたオーバーワークが原因で悪化する事が時々あります。そのため「動くと症状が重くなる」と思っている方が多くいらっしゃいます。
しかし、安静にしてばかりいると体力は落ちてしまいます。長期間動かない状況が続くと、デコンディショニングと呼ばれる状態になります。これは身体を動かない事によって起こる異変の総称を指します。
実は心臓が悪い方は、心不全になるだけでこのデコンディショニングが進行します。筋力や肺活量の低下、立ちくらみ、ふらつきなどが出てきて日々の生活が難しくなり、精神的な不安から鬱になったり自律神経が不安定になり、増悪・寛解を繰り返して予後を悪くしていくんですね。
心不全ステージ分類(心不全 病みの軌跡) 心不全手帳 第3版より抜粋
こういった悪循環に陥らないためにも、日頃から適切な運動を継続して行う事が大切になります。また骨格筋には局所の血液を心臓に返すポンプの働きがあり、心臓の負担を減らすという意味でも重要です。図に示されるように、実は運動能力が落ちると心疾患リスクが増えてくるんです。
出典:Circulation, 1999,99,1173-1182
では、適切な運動ってどれくらいのものを言うんでしょう。簡単な目安としては、軽く汗ばむ程度、呼吸は早くなるが人と会話ができる程度の運動とされています。ただし通常の心疾患をお持ちの方や著しい肥満、虚弱の方は必ずしもこの指標が妥当でない場合があり、負荷の大きい運動は症状が悪化する可能性があります。
当院の心臓リハビリテーションでは、まず実施前に心肺運動負荷試験で運動中の呼気ガスを分析して呼吸、循環、代謝の総合的な評価を行い、その人にとっての安全かつ効果的な運動指標を把握して運動プログラムを作っています。また運動を行う際には血圧計や酸素飽和度、心電図モニターなどで循環動態を適宜チェックして過負荷にならないような配慮をしています
心肺運動負荷試験(CPx)
具体的な運動内容としては、前半に動画によるストレッチ、エアロビクスで身体を動かす前の怪我の予防、トレーニング効率の増大を図り、レッドコードなどを使用して個人ではカバーしきれない箇所の柔軟性やバランス、筋力強化を行ったりしています。後半は自転車エルゴメーターやトレッドミルなどの有酸素運動が主体になります。実際のリハビリ器具の使い方や内容に関してはホームページ内にも取り上げていますのでご参考にしてください。 もちろん、運動以外の様々な側面からライフスタイルを構築していく事が心臓病の予後改善につながるため、多職種が包括的にアプローチする事によっても心疾患を持つ方の生活をサポートしています。
当院の実際の心臓リハビリテーションの様子
実際のリハビリ中の動画も当院の公式インスタグラムに挙げているので、そちらもぜひご覧になってください。
今回は、心臓病にとってなぜ運動が大切かをお話させて貰いました。日頃から運動をしている人も、その内容が果たして自分にとって適切なものかどうかは検査をしてみないと分かりません。心臓病の方はこれを機に一度自分の生活を見直してみませんか。きっと自分の世界観の中で新たな発見がある筈です。
最後まで読んでいただき有り難うございました。